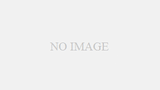かの有名なロバート・キヨサキの本に「キャッシュフロー・クワドラント」というものがある。その本には、いわゆる収入の流れには4つの形態(雇用者/E・個人事業主/S・起業家/B・投資家/I)があることが説明されている。
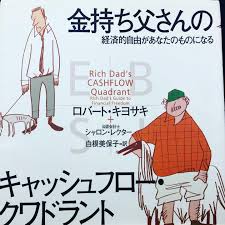
しかし、私は過去に数々の経験して改めて自分がたどってきた道を振り返ってみた時に、キャッシュフロー・クワドラントは、実は「クワドラント」なのではなく「レイヤー」として表現した方がより実態に合っているのではないかと考えるようになった。
また、持たざる者が経済的に成功したいと考えた場合、この世の中が「クワドラント」ではなく「レイヤー」だというのを正しく認識しておかないと、のちのち大きな問題を起業家が抱えざるを得ない状況になる可能性があることに気が付いた。そのことについて、この記事で言語化を試みたい。
ロバート・キヨサキを知らない人は少ないだろう。2000年代初頭に大ヒットとなった「金持ち父さん貧乏父さん」の著者だ。このロバート・キヨサキの2作目の著書が冒頭に取り上げた「金持ち父さんのキャッシュフロー・クワドラント」である。実は、私はこの従来型キャッシュフロー・クワドラントには、誤解につながりやすい大きな問題があるのではと考えるようになった。例えば典型的な4象限のあの図である。
ロバート・キヨサキがキャッシュフローによって4つの区分に抽象化してくれた功績は大きい。しかし、ぱっと見、例えばE(従業員)の人たちが読者の大半であろうから、この立場について考えてみると、彼らは、資産を増やすために、裕福になるために、一番最初にS(個人事業主)、B(起業家)、I(投資家)のうち、どこを目指せばいいのだろうか?従来のキャッシュフロー・クワドラント形式だと、向かうべき方向性がわからない。早く裕福になりたい人や成長を急ぐ人は、まず右下の「I(投資家)」に目が向いてしまうのではないだろうか?
昨今、サラリーマン大家さんやNISAなどが流行っている。株式市場はまるで桐谷さんを客寄せパンダのごとく祭り上げ、素人を感化して株式投資させようと躍起になっている。NISAなどは国主導で、E(従業員)の人たちの虎の子の貯金を株式市場に流し込むための劇場装置の様相を呈している。どうしたら持たざる凡人が道を間違うことなく、正しい順序で資産を築いていけるようにできるだろうか?残念ながらロバート・キヨサキの複数ある著書のどれを見ても、その答え(順番に関する答え)は載っていない。
私自身、この答えを見出すために様々な本を読み漁った。その思考過程は複雑になるのでここでは省くが、結論はこうだ。キャッシュフロー・クワドラントによる4象限での表示ではなく、下から「E(従業員)」→「S(個人事業主)」→「B(起業家)」→「I(投資家)」のピラミッド構造こそが、より世の中の実態や仕組みを表している。
また以上から、以下の教訓が導き出せる。
①金銭的な意味での支配構造や、持たざる者が持てるようになるために踏むべき段階という意味で、クワドラント表示よりレイヤー表示の方がより現実に近い表示である。このため、このレイヤー表示とした方が、上を目指す者に、自分が今、登るべき山の何合目にいるかを認識させやすく、より失敗も局限させやすい。
②持たざる凡人は、上を目指すにあたって決して、特に「S(個人事業主)」を飛び越してはならない。「S(個人事業主)」を飛び越したり、またそれぞれのステップで必要なスキルや知識を身につけていない場合、もし失敗したら、簡単に落ちるところまで落ちることになる。つまり「まずは副業(Sペッグ)から始めよ」ということである。起業家は、もし失敗したら個人事業がセーフティネットになる。個人事業主は、もし失敗したら副業がセーフティネットになる。つまり、富士山に登るためには一合目から登り始めなければならないように、起業家として成功するためには、まずは副業という一合目から始めるべきなのである。
③どのレイヤーもカモが欲しいので「あなたも成功できる」という甘い言葉で他のレイヤーにいる人間を引き込もうと誘ってくるが、それに乗ってはいけない。乗ってしまうと無駄なお金を失ってしまう事になる。必ずこのパターンを守るとともに、そのレイヤーで十分に成長するまでは、自分のステージではない場所には手を出さない。恐ろしいことに、省いてはいけない「S(個人事業主)」だけはあまり誰もカモろうとしてこないため、まさに「E(従業員)」の人たちが見落としやすい経由地点になってしまうということも注意が必要だ。
④レイヤーの上流を目指した方がより生存に有利となる。E→S→B→Iとピラミッドを上に登っていくにつれ、より抽象的なスキルが必要になってくる。例えば下流だと具体的な金になるスキルが必要だし、上流だと市場の理解や資本政策といった具合に必要なスキルがより抽象的になっていく。このため、この上流で必要とされる汎用的な知識の方が分野を跨いでスキルを使うことができるようになるため、より生存に有利となる。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。皆さんの事業の成功を心より願っております。