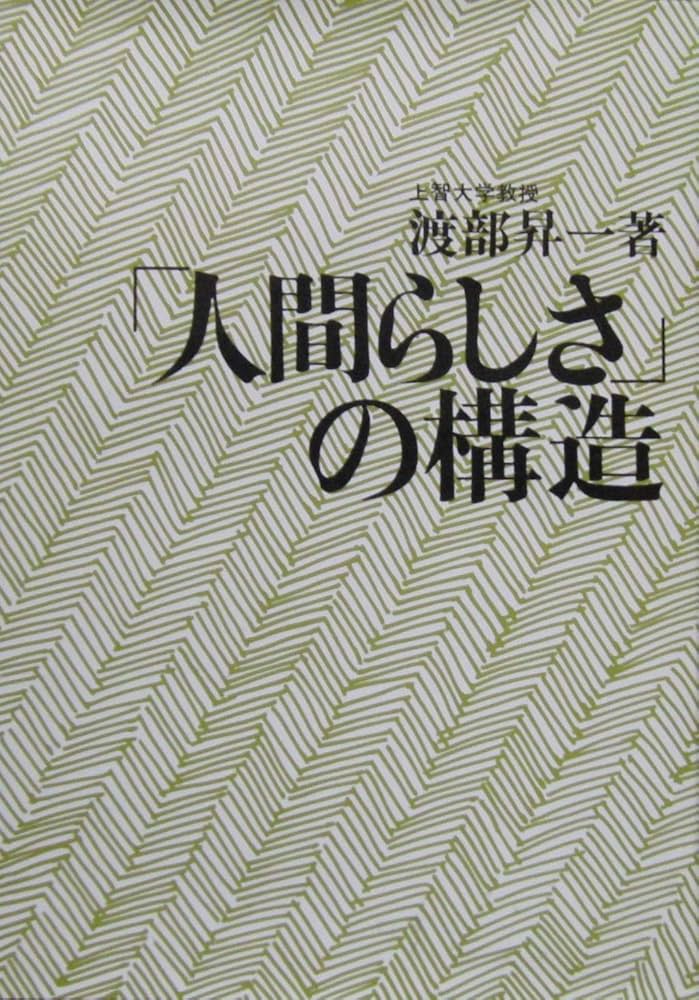私はこの本を学生時代に大学の図書館で見つけた。その頃、自分の生き方とか考え方とか方向性などについて相当迷っていて、正しい方向性を求めていた。
ある日、いつものように大学の図書館のソファーエリアで時間を過ごしていた時、近くの本棚に講談社の青い文庫本、渡部昇一著「人間らしさの構造」が、背表紙をこちらに向け、無造作に倒して置かれているのが目に留まった。その時、なぜだかその本が私に何かを訴えかけているように感じ、手に取って読み始めた。

表題からすると、古臭い根性論や精神論が書かれているのではないかと想像していたが、実際にページをめくってみると、それは人間の心のあり方を心理学的、哲学的な視点から深く掘り下げた書物であった。
中でも特に私の心に深く刻まれたのは、心の大切なあり方の一つとして語られていた「かるみ」という言葉だった。著者は、熟練した達人は素人と比較して動きが軽いと指摘し、さらに新幹線を引き合いに出し、機関車と比較して重量、スピード、そして顧客に提供できるサービスの質、あらゆる面において「かるみ」があると表現していた。そして、この「かるみ」こそが人間が目指すべき境地であると説いていた。
また、本書の中で著者は明確にデフォルト・モード・ネットワークという言葉を用いてはいないものの、まさにそれを示唆するような記述があったと今にして思う。「自分の心の声を聞ける人は少ない」「自分の心の声にしたがって生きる人間を目指すべき」というくだりである。
デフォルト・モード・ネットワークとは、脳科学において、特別なタスクを実行していない安静時に活発になる脳のネットワークのことである。リラックスした状態にある脳で、ふとした瞬間に重大な閃きが得られることは、アルキメデスが風呂場で浮力の原理を発見したエピソードなどが良い例として挙げられる。これはまさに、典型的なデフォルト・モード・ネットワークが活性化した状態だったと考えられる。
並行して、この本を手に取った頃、大学の学生寮で先輩から「何か問題にぶつかったら、紙に書き出してみるといい。自分が抱えていた問題が意外と大したことがないことがわかる」というアドバイスを受けた。今思えば、その「紙に書き出す」という行為こそがブレーンストーミングであると同時に、自分の内側にある答えを探る、すなわち自分の心の声を聞こうとする行為そのものだったのだと、数十年経った今、改めて気づかされた。
かくして、渡部昇一氏の「人間らしさの構造」は、その後の私の人生において、問題に対してブレーンストーミングやデフォルト・モード・ネットワークを通じて「自分の心の声」を聞き出し、問題解決や新たな閃きを得るための重要なきっかけとなったのである。
自分の心の声を聞けないのは、生きているとは言えないのと同じであると私は考えている。忙しい日々に追われ、外界の情報にばかり気を取られて反応的に生きている人は、週に一度でも良いから時間を作り、今一度、静かに自分自身と向き合う時間を持つべきではないだろうか。