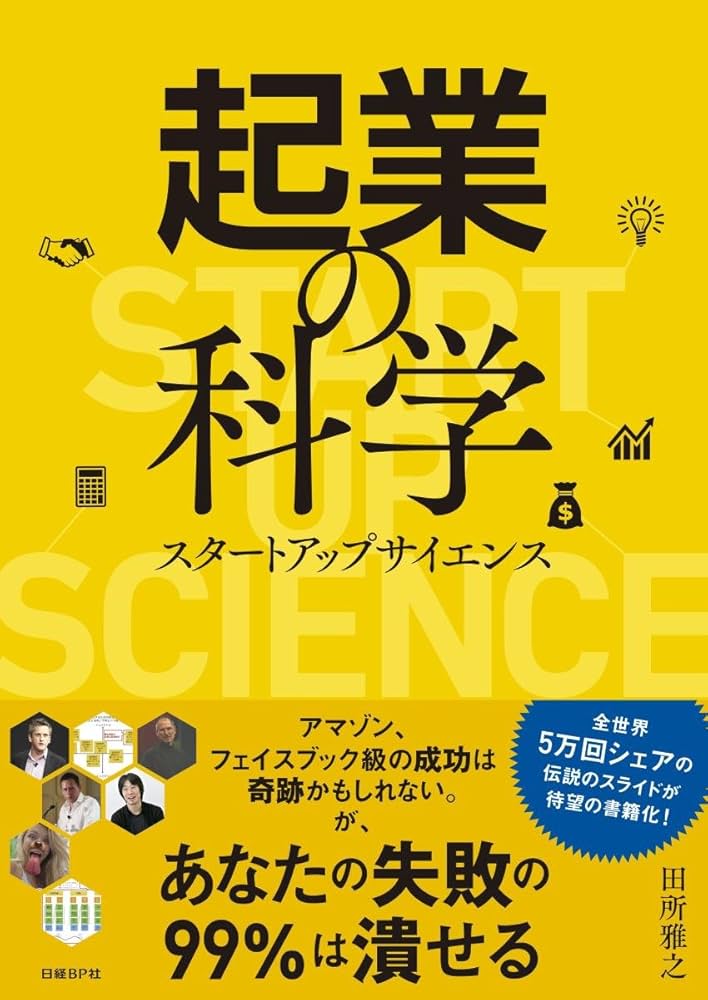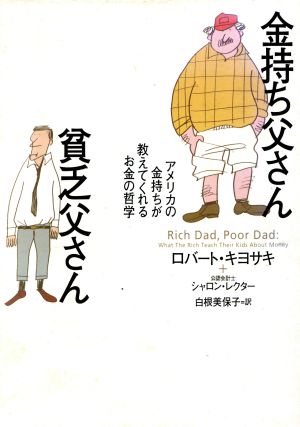前職で、幸運なことにの様々な場所に行かせてもらえ、合計12カ国14箇所を回る機会があった。その時に現地で感じたことを備忘録として書き留めておきたい。メモ書き程度の走り書きのような備忘録なのでご容赦願います。
まずは米国のハワイ。戦艦アリゾナは、本物の戦艦が見える深さに沈んでいて、その上にブリッジ状に回廊が設けられており、厳粛な雰囲気であった。また、ダイヤモンドブリッジも訪れた。クレーター型の山だが、中央から見ると意外に周囲の山は低い。近くに瀟洒な住宅街があり、通りを歩いていると家と家の間からビーチが見えるのが印象的だった。もうしばらく歩くとスーパーがあり、駐車場で男性が1人屋台でステーキを売っていた。購入するとライスも付いてきて、「アメリカ人にステーキとライスの組み合わせの良さがわかるのか!?」と驚いた記憶がある。ワイキキビーチでも泳いでみたのだが、沖の方で足を付くと、下がコンクリートになっていて、後で知ったのだがワイキキビーチそのものが人口のビーチらしく、興醒めしたのを覚えている。ワイキキビーチの近くのコンビニでアルコールでも買って飲もうかと思ったら店員から「法律で禁止されているからダメ」と言われ、この時初めて日本以外の国では路上でのアルコールが禁止されていることが多いことを知った。他の同僚はセスナを操縦できるツアーに参加したりしていて、自分も行けばよかったなどと後悔したりもした。また、他の同僚はレストランで高木ブーに遭遇したようだ。
次はメキシコのマンサニージョだ。このメキシコは別記事「メキシコのマンサニージョで爆発的に英語が喋れるようになった出来事について」に詳しく書いた。
次に訪れたのはパナマだ。パナマ運河はYouTubeの通り、水位が上下していて見応えがある。水門から水門への移動は、船の推進力ではなく、運河の両脇にあるレールの上を走る牽引車からのワイヤーで左右から引っ張り前進する形式だった。これは「曳船用機関車」というらしい。パナマの街中ではフロントガラスに「エヴァンゲリオン」と書かれたジープが駐車場に止まっているのが印象的だった。パナマの街中の人々は、自分が日本人だとわかると「東郷平八郎」や「イチロー」だとか彼らが知っている日本人の名前を叫ぶ人たちがいた。こんな辺境の国でも日本のことが知られているのが印象的だった。
次は米国はノーフォーク。ここは街中は煉瓦造りの建物や道路が非常に多い。とある建物の前で立っていると、近くにいた米国人が、確か「どこからきたのか?」みたいなたわいもない話を話しかけてきた。驚いたのが、彼はどうやら奥さんがストリッパーで、目の前の建物で今その仕事をしているので、終わるのを待っているんだとあっけらかんと答えたことだ。彼はなぜか自分の帽子についている龍の模様が描かれたピンをくれた。どうやらベトナムで第3水陸両用部隊とかいう海兵隊の部隊に所属していたそうで、その時の部隊章らしい。そんなも大切なものを自分が貰ってしまって良かったのだろうかと今にして思ってしまっている。
次はイギリスのポーツマス。噂のフィッシュ&チップスも食べたが、別に不味くはなかった。どのお店の店員さんも笑顔で民度が高く、住み心地の良さそうな国だという印象だ。HMS Victoryも見に行き、船内で当時の船員が食べていたというクッキーも買って食べてみたりした。
次はドイツのハンブルク。ここはビールとソーセージと魚料理がとてもおいしかった。学生時代ドイツ語をとっていたので、滞在中は片言のドイツ語で乗り切った。ドイツ語は英語と単語が似ているので、使用する単語はドイツ語だが、文法は英語という滅茶苦茶な力技で乗り切った。しかし、今覚えているのは一つだけ。「ツァーレン・ビッテ(お勘定をお願いします)」だ。また別の同僚はハンブルクの有名な歓楽街に集団で行ったらしく、地元紙に写真付きで第一面に「日本の皆さんようこそ〇〇〇〇へ(〇〇〇〇は風俗街の名前。レーパーバーンとかだったかもしれない。)」と掲載されてしまっていた。日本の恥である。
次はロシアのサンクトペテルブルグ。観光ガイドの人が盛んに「ピョートル大帝」を連呼する。どうやらロシア人はこのピョートル大帝にかなりの誇りを持っているらしい。別の同僚はロシア人にヒューミントをかけられそうになったらしく、かなりしつこく足止めされてチームの集合時に間に合わず、別の同僚にかなり詰められていた。いまだにそういうことを平気でするロシア人がいるのが恐ろしい。おそらく共産圏を訪問したらどの国でもそういうことをやられる可能性はあるのだろう。
次はフランスのブレスト。街中に日本の漫画専門店があるのが驚き。フランスの郵便ポストは黄色い。肉が食べたくなってレストランに入ってステーキを注文するが、英語が通じないため仕方なく紙ナプキンに牛がフォークを持ってステーキを刺している絵を書いたら本当にステーキを持ってきてくれた。フランスでフレンチの本場だからどの食堂も料理が美味しいのかと思っていたがそんなことはなく、普通の味だった。南部の田舎町でフリーマーケットをやっていて、いろいろ古い味のある骨董品を売っていて買って帰りたかったのだが、荷物は作れないので断念したのが残念だった。
次はマルタのバレッタ。基本的にここは薄いクリーム色の大きなブロックで建物や道路が作られているため、かなり異界感、別世界観を強く感じた。この記事で紹介した海外の中で最も、再び訪れたい地域だ。
次はトルコのイスタンブール。ここでは例のごとくトルコアイスの店主にお約束で弄ばれた。アイスの味は覚えていない。とにかく印象的だったのが、よってくるトルコ人の目がみなハゲタカの目だったことだ。口では優しく「観光案内します」とか「美味しいレストラン紹介します」とか言っていたが、目が真剣でまるで殺人鬼のような目つきでこちらを見てくる。トルコより貧しい国にも何回か行ったことがあるし、そもそもトルコはそんなに貧しい国ではないと思っていたのだが、とにかく現地人の目つきは怖かった。ブルーモスクは荘厳な雰囲気だった。生まれて初めてここでアダナケバブとかいう名前の辛いケバブを食べた。
次はエジプトのポートサイド。エジプトは赤道や海に近いので暑い印象だが、湿度が低いため、意外に蒸し暑さは感じなかった。物乞いっぽい少女がポケットティッシュを1ドルで買ってくれとうるさかったので買ってしまった。当時、Webメールはまだ種類が少なく、自分はHotmailを使用していたのだが、ある時日本に連絡を取りたくなり、街中でネカフェを探し出してブラウザでこのHotmailが使えて感動した記憶がある。コンビニみたいなお店でミネラルウォーターを買ったのだが、かなり酷い下痢になってしまった。どうやらこの地域は水は日本とは違い硬水のようで、人によってはお腹が緩くなりやすいそうだ。
次はインドのムンバイ。エレファンタ島のシヴァ神の石像も見に行った。日本だと車がクラクションを鳴らすのは危険が迫った時だけだが、ムンバイの街中のタクシーはそうではなく、彼らは景気付けにクラクションを鳴らす。20秒ごとには警笛を鳴らしているイメージだ。誰かが鳴らしたら鳴らす、対向車が鳴らしたら鳴らす、後ろの車が鳴らしたら鳴らすといったイメージだ。まるでDJか何かのようだ。別の同僚はインドは街中であちこちに普通に人の夕ヒ体が転がっているのを見て夕ヒ生観が変わったと言っていたが、自分は街中でそれ(夕ヒ体)を目にすることはなかった。
次はカンボジアのシアヌークビル。行った時はちょうど雨季であり、街中は20cm近く水没していて、車が水飛沫を上げながら走っていた。この街ではタクシーはいわゆるバイクタクシーが主流で、一日借り切っても大した値段ではないので、観光の際は一緒に行動した同僚と数台のバイクタクシーを借り切って街中を観光して回った。バイクタクシーを借りる際、ホテル入り口を出ると、敷地の向こうでバイクタクシーの群れが一斉にみな手を上げてこっちに来いと言わんばかりに手招きしているのがまるでゲームのワンシーンのようで印象的だった。
最後は米国のニューポート。ロードアイランド州だ。ここはBoston国際空港に降りてからバスでプロビデンスを経由して向かった。漁業の街で、クラムチャウダーなどが名産らしい。ホエールズとかいうクラフトビールが美味しかった。休日にプロビデンスまで同僚と出かけて初めてロブスターを食べた。またアムトラックを利用してNYまで行き、セントラルパークやトランプタワー、ツインタワー、エンパイアステートビルなどを見て回った。
以上、12ヶ国14箇所の海外渡航記でした。ここまでお読みいただきありがとうございます。