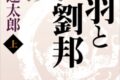デ・ハビラント・コメットと聞いてピンとくる人はもうほとんどいないであろう。かつてイギリスで一世を風靡した航空機である。この機体は全金属製、当時はまだ少なかったジェットエンジン搭載と、時代の最先端をゆく旅客機であった。

デビュー当初は高い人気を誇ったコメットだが、その後、相次いで空中爆発事故を起こすことになる。当時のチャーチル首相が、事故原因の徹底的な究明を指示したという逸話が残っているほど、社会的な衝撃は大きかった。
事故原因を特定するために、技術者たちは前例のない検証方法を採用した。それは、実機を巨大な水槽に沈め、飛行中の機体にかかるであろう圧力の変化を人工的に再現するというものだった。この実験の結果、地上と高高度の気圧差によって機体の金属に疲労が蓄積し、それが原因で空中分解に至ったことが判明した。それまで考慮されていなかった金属疲労という概念が、航空機の設計において重要な要素であることを示したのだ。
この事故によって、コメットを製造したデ・ハビラント社は、ボーイングなどの後発メーカーに市場シェアを奪われ、最終的には他社に吸収されることになった。しかし、コメットの悲劇は、航空業界に金属疲労に対する理解と、フェールセーフ設計という安全思想の重要性を深く認識させるという、重要な教訓を残した。
この事故の記事から私が得た教訓は、何か大きな事を成し遂げようとする場合、事前の検証がいかに重要であるか、ということだ。それは航空機の製造に限らず、大規模な行事の企画、新しい製品の開発、あるいは危険を伴う移動手段の確立など、様々な分野に共通して言える。
特に、なんとなく表面的なテストだけを行った場合、本番になって初めて予期せぬ問題が顕在化する可能性がある。そうなってからでは、多くの場合、事態の収拾は困難を極める。取り返しのつかない損失につながることも少なくない。
したがって、テストにおいては、経済的な合理性も考慮しつつ、可能な限り現実に近い状況を模擬することが不可欠だ。例えば、イベントであればリハーサルを重ね、様々な状況を想定したシミュレーションを行う。製品開発であれば、実際の使用環境に近い条件下での耐久テストや負荷テストを徹底的に行う。危険な移動手段であれば、より現実に近い途中の経路をシミュレートしておく必要がある。
「まさかこんなことが起こるとは思わなかった」という事態を防ぐためには、想像力を働かせ、あらゆる可能性を考慮した上で、「より現実に近い環境でテストを行う」こと。これが私のポリシーであり、現在様々な場面で実践している教訓である。